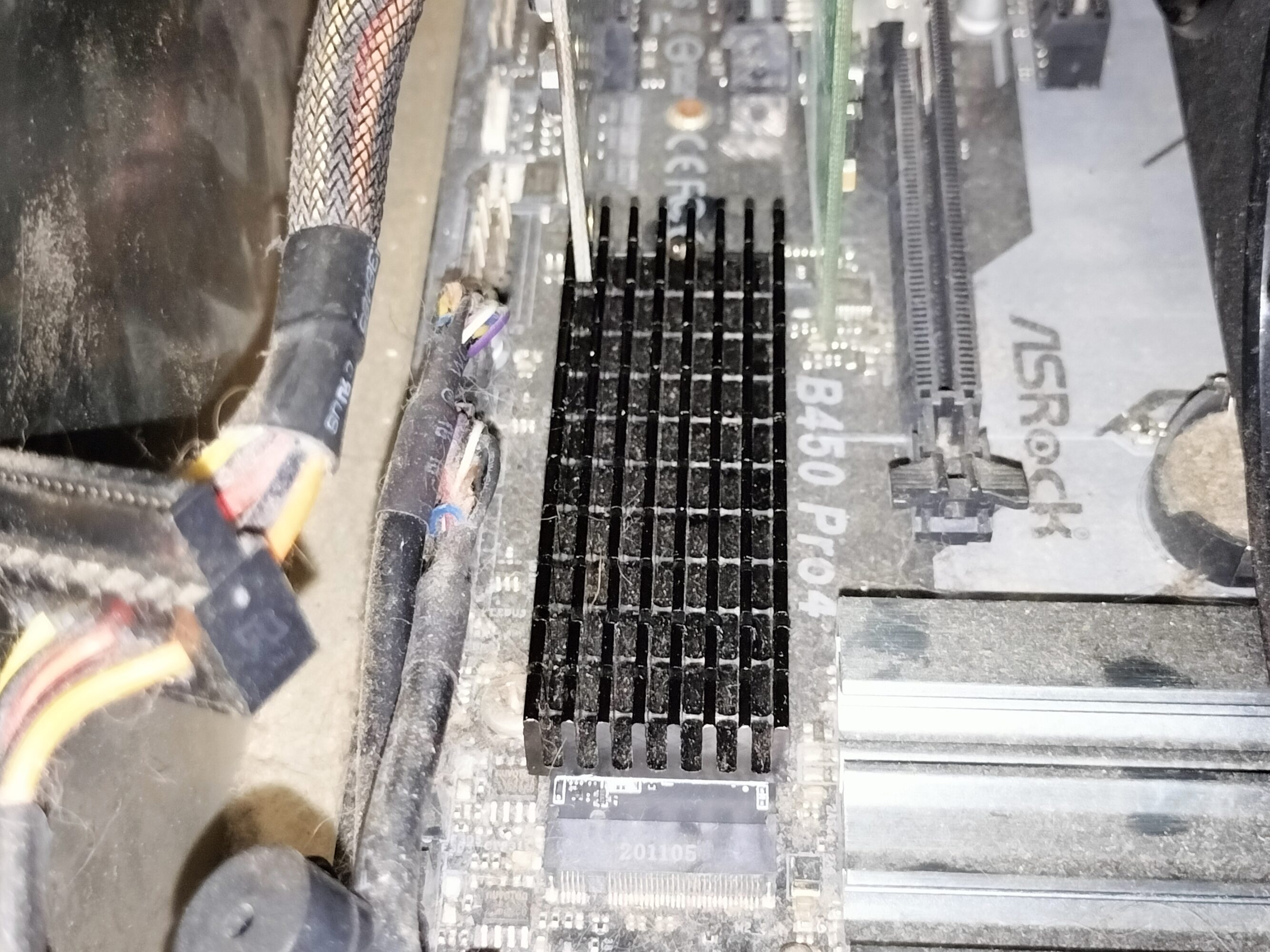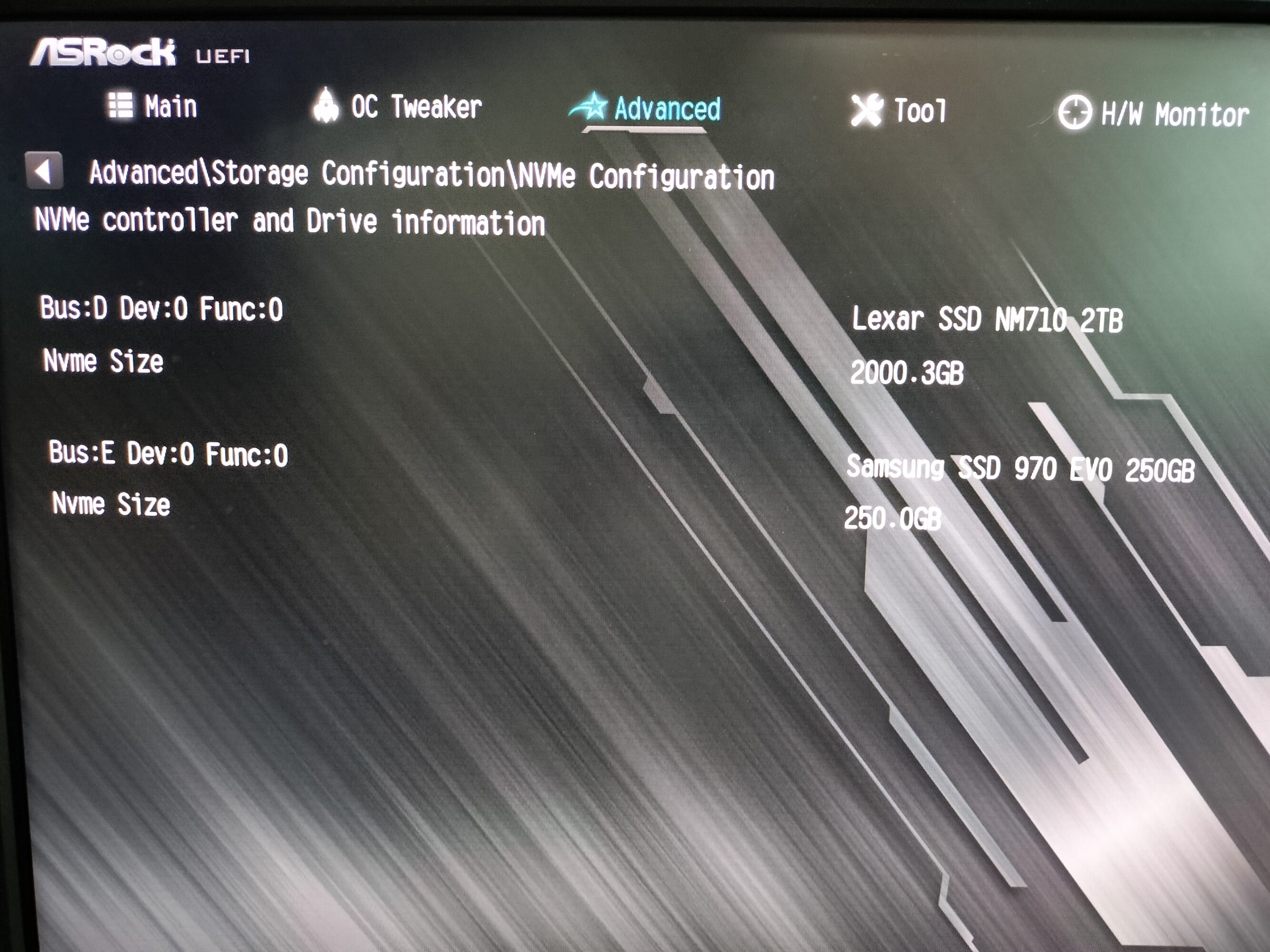もう既にODOメーター200,000kmを越え、弄らないと行けないところが諸々増えてきてるわけですが。
とりあえずこの数年で歴代交換したであろう箇所は
と、やばそうな所やちょっと足したい所などはチマチマやってます。
リアがまだ手付かずなんですが、そんなにへたってきていなさそうな気配だったんで今まで手付かずです。
ただそろそろやらないとだろうなぁという頃合いになってきてる。
リアの足回りは後で時間を作って盛大にオーバーホールかけるしか無い。
リアのダブルウィッシュボーンを構成しているパーツ随所にゴムブッシュがあるにでそいつを全部打ち替える必要がある。
リンクの分解は自宅でもできるが、打ち替えは油圧プレスがウチにはないのでできない。
というわけで後回し。
そしてそろそろハブのベアリング回りも交換したいなーとなったので、リアハブベアリング交換です。

サイドブレーキ効いてるウチにセンターロックナットをインパクトで外しておきます。

サイドブレーキを開放して、ブレーキのドラム部分にあるネジ穴2箇所にM8のボルトを挿していくとディスクドラムが浮いてくるので外して行きます。
ブレーキディスクドラムを外すと出てくるサイドブレーキシューとリアハブ

アストロプロダクツのハブプーラーをカマして、スピンナーハンドルでゴリゴリ回して行くと

サイドブレーキ機構と共にハブベアリングがスポッと外れる。
ベアリング外周が錆びて膨れていてサイドブレーキ裏のプレートから外れてくれなかったので、ベアリングをハンマーでガンガン裏からひっぱたいて外す。
左側のサイドブレーキシューが邪魔になるので、留められてるクリップピンを外して少し浮かせて上げるとベアリングがこのように取り外せます。

あとは新しいベアリングをサイドブレーキ機構を通してシャフトに挿入して、裏から四本留められてるボルトを固定するだけ。

ついでなので、リアブレーキキャリパーのオーバーホール。
オーバーホールキットは左右2セットなので、どうせ両側ハブベアリング換えるので、キャリパーも両側実施。
ブレーキペダルをガンガン踏んでピストンを露出させ、抜けそうな所でスクリューバルブを開けて最後は指でグリグリやってくると抜ける。

シリンダーも内側は特に錆びて居らず、ピン類もグリスにまみれていたので腐食無し。

ピストン内側も錆び無し。
ブーツやシールゴムが劣化していて水が混入してくるとシリンダーやピストンが錆びて固着し、ブレーキがかからなくなります。
定期的な確認とオーバーホールは必要なのですが、まだまだ大丈夫だったようでしたが、予防交換大好きなので交換。

ブーツ類は凸凹で噛み合うようになってるので、キャリパー側、シリンダー側を美味くはめ込んで挿入。
スクリューバルブは緩めたままでとりあえずピストンを一番奥まで押し込む。
あとはブレーキフルードのエア抜きを行う為、スクリューバルブにホースを繋いで負圧装置で吸い出していく。
フルードをある程度吸い取ったらスクリューバルブをキュッと閉めてキャップ被せる。

一通りボルト締め終えたらハブロックナットを200N・mでキュッと締め、空回りしないようにロックナットをシャフトの窪みに合わせて貫通マイナスドライバーを当ててガツンがツン凹ませて終わり。

結構錆び錆び。
この後試走したところ、以前はあった変なゴロゴロ感が無くなったので、やはりガタが来ていたんだろうと自己満足。